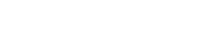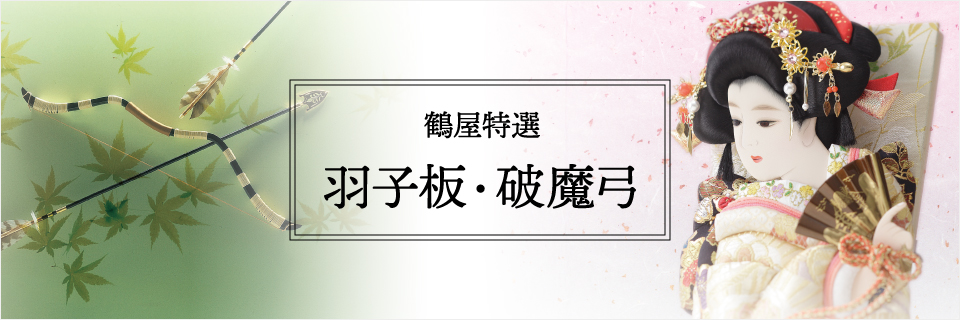2025年破魔弓・羽子板販売会は終了しました
羽子板〈清らかに美しく、永久の幸福を願う〉
羽子板は『邪気』をはね(羽根)のける女の子の大切なおまもりです。
羽子板の起源と由来
室町時代からのお正月の遊び物や贈り物として
古くは15世紀の宮中で、羽根つきが行われたそうです。また、飾り用として、足利将軍が年末に宮中に羽子板を贈っています。 でもこの頃はまだ上流階級だけの習慣だったそうです。
江戸時代に大流行した、遊び心ふくらむ多彩な押絵(おしえ)羽子板
江戸時代以降、羽子板に描かれた絵で演技をかつぐようになりました。 それがどんどんグレードアップし、押絵(※1)を応用した「押絵羽子板」が登場し、その技術は、明治時代には東京の職人芸として完成されていきました。
※1 押絵・・・・厚紙に羽二重(はぶたえ)の布をかぶせ、立体的な絵柄を仕上げます。屏風、香箱、など装飾技法のひとつです。
現在まで時代の流行を映す風物詩。今も大賑わいの浅草羽子板市
江戸時代初期に始まり、毎年12月17日、18日、19日の3日間、浅草寺の境内で行われる「歳の市」。 そこでの主要商品が明治中頃から羽子板となり、昭和25年頃には「羽子板市」の名前で定着しました。 現在も、歌舞伎役者に加え、芸能人やスポーツ選手など、世間をにぎわす人気者を描いた羽子板が来訪者を楽しませてくれます。
新春の遊びから飾るものへ
現在は飾る羽子板が主ですが、羽根つきは江戸時代に新春の遊びとして浸透し、正月には小気味のいい羽子板の音と、女の子のはしゃぎ声が聞こえました。
羽子板の選び方・飾り方(よくあるご質問)
Q. なぜ羽子板を飾るの?
A. 羽子板には女の子の無病息災のお守りの意味合いがあります。 羽子板で突く「無患子」という玉は、「こどもが患わない」という意味を含み、昔は羽根をトンボに見立て、 トンボが伝染病を引き起こす蚊を食べてくれることから夏になっても蚊に食われないと信じられてきました。羽子板には子供の無事を願う親心が込められています。
Q. 飾る時期は?
A. 女の子の初正月を祝うための品ですので、12月の中旬以降に飾るのが良いとされています。 12月29日(苦立て、二重苦)や12月31日(一夜飾り)に飾るのは縁起が悪いと言われています。
Q. しまう時期は?
A. 昔から小正月(1月15日頃)に「どんど焼き」という行事で注連縄や松飾、書初め、羽根を突いて壊れた羽子板などを焼く習慣がありましたので、 15日前後の土日にしまう方が多いようです(地域によって異なります)。
お子様の無病息災、魔除けを祈る縁起物ですので、一年中飾っておくのも良いでしょう。 しまわれた場合も、雛人形の時期には脇飾りとして一緒に飾ると、より華やかにお祝いが出来ます。
Q. 女の子がいくつになるまで飾るの?
本来は子どもを中心とした羽根突き遊びの道具に縁起を込めて用いられてきたものですから、大人になるまで毎年飾り、家族と一緒にお正月を祝いましょう。
Q. 羽子板はどうやって飾る?
A. 羽子板を飾るケースに入れるのが一般的ですが、スタンドに立てて飾ることもあります。
Q. 飾りのもの羽子板は遊びに使ってはいけないの?
A. 正月飾りとしてお祝い用に作られた羽子板は、表面に押絵の人形が施され、乱暴に扱えば押絵を取り付けた金の金具も抜けてしまいます。大事に飾ることをおすすめします。
破魔弓〈強く、勇ましく、健やかな成長を願う〉
破魔弓は邪気をはらい、悪魔を恐れさせる男の子の大切なお守りです
破魔弓の起源と由来
魔除け・豊作祈願・伝説人々の願いがこもった弓矢の役割として
古くは縄文時代から狩猟目的で作られた弓矢。その威力から、次第に神聖な道具としても扱われるようになります。 平穏な世界と人々の無事を祈る「魔除け神事」、そして豊作を占う競技などに登場しました。
弓矢が魔除けのアイテムとなった、神聖な儀式のあれこれ
宮中では古くから魔除けや年占いを目的とした弓矢の行事がありました。 正月に行われる弓で的を射る「射礼(しゃらい)」や、皇子が誕生したときや産湯を使うときなどに弓弦を鳴らす「鳴弦(めいげん)の儀」などが今でも皇室で受け継がれています。 いずれも世の中の平和と天皇家の健康を祈るものです。
鎌倉時代には強い武士になって出世する願いを込めて
破魔弓が現在のような弓と矢を組み合わせた形になったのは鎌倉時代。 武家の男児が立派な武士として名をあげるようにと願い、男の子の初正月に手遊びで使えるような弓矢を贈りました。 男の子にしてみれば、おもちゃの弓矢は大興奮のアイテム。それが城下町を中心に一般庶民へと広まっていきます。
江戸時代には工芸品として磨きがかかり、飾り物として定着
江戸時代になると豪華な破魔弓が作られるようになり、飾ることが主流になりました。 男の子の健やかな成長の無事を託した縁起物として、装飾された弓と矢が初正月や初節句に贈られました。より美しく、ゴージャスに。それもまた親心だったのです。
現在では今年もよい年でありますようにとの願いを込めた開運の縁起物として
破魔弓だけでなく、破魔矢も優秀なお守りです。正月神社に詣でると、その年の干支の絵馬や鈴がついた破魔矢を求めることができます。 一年の厄除けを祈願して、飾りましょう。
家屋の守り神として新築の上棟式にも登場
破魔弓や破魔矢は、家の棟上時に行う上棟式で屋根の上に飾る風習もあります。 これまでの工事が無事に進んだ感謝の気持ちや、竣工まで禍いなく幸多いご加護を祈ります。
破魔弓の選び方・飾り方(よくあるご質問)
Q. なぜ破魔弓を飾るの?
A. 破魔弓には男の子の魔除け、厄払いの意味合いがあります。 弓の的を昔は「ハマ」と呼びました。破魔弓はこの「ハマ」に漢字を当てはめ神社の破魔矢と同じように、弓矢の持つ霊的な力を信じ飾られてきました。
Q. 飾る時期は?
A. 初正月に飾る破魔弓は、12月中旬以降に飾るのが良いとされています。12月29日(苦立て、二重苦)や12月31日(一夜飾り)に飾るのは縁起が悪いと言われています。
Q. しまう時期は?
A. 昔から小正月(1月15日頃)に「どんど焼き」という行事で注連縄や松飾、書初め、羽根を突いて壊れた羽子板などを焼く習慣がありましたので、 15日前後の土日にしまう方が多いようです(地域によって異なります)。
お子様の無病息災、魔除けを祈る縁起物ですので、一年中飾っておくのも良いでしょう。 しまわれた場合も、五月人形の時期には脇飾りとして一緒に飾ると、より華やかにお祝いが出来ます。
本来は子どもを中心とした羽根突き遊びの道具に縁起を込めて用いられてきたものですから、大人になるまで毎年飾り、家族と一緒にお正月を祝いましょう。
Q. 選ぶポイントは?
A. 破魔弓は弓と矢のバランスや全体の力強さ、美しさを見て気に入ったデザインの物を選ばれるといいでしょう。 ケースに入っていますので、ケースの素材や色も選ぶ際のポイントになります。
(C) Tsuruya Department Store Co., Ltd All rights reserved.