
- ’ك‰®ƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒXƒgƒA
- 100پ“ŒF–{•S‰ف“X
- گl‚ئƒ‚ƒm‚جƒXƒgپ[ƒٹپ[
- Vol.5 “V‚جگ»’ƒ‰€
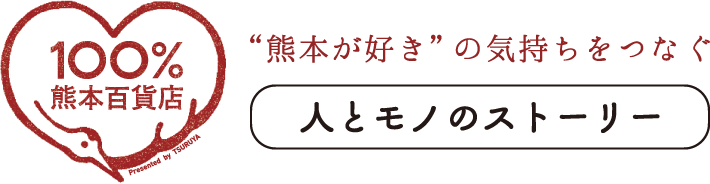 Vol.5
“V‚جگ»’ƒ‰€
Vol.5
“V‚جگ»’ƒ‰€
پ¦Œfچع‰؟ٹi‚حپA‹Œگإ—¦‚إ•\ژ¦‚µ‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB
‡€“V‹َ‚ج’ƒ”¨‡پ‚إپA
–³”_–ٍپA–³”ى—؟‚إˆç‚ؤ‚½
ڈa‚ف‚ج‚ب‚¢کaچg’ƒ
•Wچ‚600m‚ةچL‚ھ‚é“V‹َ‚ج’ƒ”¨
پu‚±‚±‚ھپAژ„‚½‚؟‚جƒXƒ^پ[ƒg‚ج’n‚إ‚·پvپB
گ…–“ژs’†گS•”‚©‚çژش‚إ30•ھ‚ظ‚اپBژژ™“‡Œ§‚ئ‚جŒ§‹«‚ةپA‘N‚â‚©‚ب—خگF‚ج—t‚ة•¢‚ي‚ꂽ’ƒ‰€‚ھچL‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBˆؤ“à‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚ء‚½‚ج‚حپAپu“V‚جگ»’ƒ‰€پv‚ج‘م•\ژو’÷–ً‚إپAژO‘م–ع‚ج“V–ىچ_‚³‚ٌپBگ…–“‚جٹC‚ً‹²‚ٌ‚إ“‡Œ´‰_گهٹx‚ھ–]‚كپAگU‚èŒü‚‚ئژژ™“‡‚ج–¶“‡‚ًŒ©“n‚¹‚é•Wچ‚600m‚جچ‚Œ´پB‡€“V‹َ‚ج’ƒ”¨‡پ‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚ھ‚ز‚ء‚½‚è‚ج•—Œi‚ةˆ³“|‚³‚ê‚ـ‚·پB
“ىŒü‚«‚جژخ–ت‚ة‚حگ^‰ؤ‚ج‘¾—z‚ھŒµ‚µ‚ڈئ‚è‚آ‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپAگS’n‚و‚¢•—‚àگپ‚«”²‚¯‚ـ‚·پBپuگخ‚ھ”ٍ‚ش‚ظ‚ا‹‚¢•—‚ھگپ‚‚±‚ئ‚©‚çپA‡€گخ”ٍپi‚¢‚µ‚ئ‚رپj’n‹و‡پ‚ئ‚¢‚¤–¼‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پv‚ئ‹³‚¦‚ؤ‚‚ê‚ـ‚·پB•½–ى•”‚ئ‚ج‰·“xچ·‚ھ‘ه‚«‚¢چ‚—â’n‚إپAٹ¦’g‚جچ·‚ھ‘ه‚«‚پA“yڈë‚ح‰خژRٹD“y‚جگش“yپB—ا‚¢‚¨’ƒ‚ھˆç‚آڈًŒڈ‚ً”ُ‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
ˆê‘ر‚حپA90”N‚ظ‚ا‘O‚ةٹJ‘ٌ‚³‚êپA‚¨’ƒ‚ج–ط‚جƒ^ƒl‚ھگA‚¦‚ç‚ê‚ؤچح”|‚ھژn‚ـ‚ء‚½ڈêڈٹپB‘و“ٌژںگ¢ٹE‘هگي’†‚ةˆê’U‚حچr‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚»‚¤‚إ‚·‚ھپAپuژ„‚ج‘c•ƒ‚½‚؟‚ھگيŒم‚جٹJ‘ٌ’c‚ئ‚µ‚ؤ“üگA‚µپAچف—ˆژي‚ھˆç‚ء‚ؤ‚¢‚½’ƒ”¨‚ًچؤگ¶پB‚»‚µ‚ؤ•ƒپAژ„‚ئ‘مپXژَ‚¯Œp‚¢‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پB”NپXپAŒمŒpژز‚ھ‚¢‚ب‚‚ب‚ء‚½’ƒ‰€‚ً—a‚©‚邱‚ئ‚à‘‚¦پA’ƒ‰€‚ج–تگد‚ح11ƒwƒNƒ^پ[ƒ‹‚ةپB–ٌ12•iژي‚ً‚Sگl‚إٹا—‚µ‚ؤ‚¢‚ؤپAچح”|‚©‚çگ»•i‰»پA”ج”„‚à‰ئ‘°‚إچs‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پv‚ئ“V–ى‚³‚ٌپB
90”N‚جŒأ–ط‚ً–³”_–ٍپA–³”ى—؟‚إچح”|‚·‚é
“V–ى‚³‚ٌ‚ھŒ»چفژو‚è‘g‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ج‚حپA90”N‘O‚ةگA‚¦‚ç‚ꂽچف—ˆ‚جŒأ–ط‚ًٹا—‚µپA‚»‚ج’ƒ—t‚ًگ»•i‰»‚·‚邱‚ئپBپu“V‚جگ»’ƒ‰€پv‚إ‚ح’ƒ‰€‘S‘ج‚ج”¼•ھ‹ك‚‚ًچف—ˆژي‚ھگè‚ك‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBŒ»چفپAژsڈê‚ة—¬’ت‚µ‚ؤ‚¢‚邨’ƒ‚ج‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚حٹا—‚µ‚â‚·‚–،‚ھˆہ’肵‚ؤ‚¢‚é•iژي’ƒ‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é‚à‚جپBچف—ˆژي‚ًژc‚µ‚ؤ‚¢‚é’ƒ‰€‚ح‘Sچ‘‚إ‚àٹَڈ‚ب‚ج‚إ‚·پB
‚»‚ج——R‚جˆê‚آ‚حپAگ…–“•a‚¾‚ئ“V–ى‚³‚ٌپBپuژY’n‚ھ‡€گ…–“‡پ‚ئ‚¢‚¤‚¾‚¯‚إپA”_ژY•¨‚ھ”„‚ê‚ب‚©‚ء‚½ژ‘م‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پBگV‚µ‚¢•iژي‚ةگط‚è‘ض‚¦‚邽‚ك‚ج“ٹژ‘‚à“‚¢ڈَ‹µ‚إ‚µ‚½پB‚»‚ٌ‚ب’†پA•ƒ‚½‚؟‚حٹو’£‚ء‚ؤچف—ˆژي‚جچح”|‚ً‘±‚¯‚ؤ‚«‚½‚ٌ‚إ‚·پBژ„‚حپA•ƒ‚جژp‚©‚çŒp‘±‚·‚邱‚ئ‚ج‘هگط‚³‚ًٹw‚ر‚ـ‚µ‚½پv‚ئکb‚µ‚ـ‚·پB“–ژ‚ح‹t‹«‚ةٹ´‚¶‚ç‚ꂽ‚±‚ئ‚ھپAچ،‚إ‚ح90”N‚جڈd‚ف‚ئ‚ب‚ء‚ؤ“V–ى‚³‚ٌ‚ھ—‘z‚ئ‚·‚邨’ƒچى‚è‚ًژx‚¦‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·پB
‰ء‚¦‚ؤپA“V–ى‚³‚ٌ‚½‚؟‚ھ‘هگط‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپA•ƒگe‚ج‘م‚©‚çژn‚ك‚½–³”_–ٍپA–³”ى—؟‚ة‚و‚éچح”|•û–@پBڈœ‘گچـ‚àژg‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB’¼ژث“ْŒُ‚ًژص‚é‚à‚ج‚ھ‚ب‚¢’ƒ‰€‚إ‚جگ^‰ؤ‚ج‘گژو‚è‚ح‰½‚و‚è‘ه•دپB‚µ‚©‚µپAپuˆہ‘S‚إ‚¨‚¢‚µ‚¢‚¨’ƒ‚ًچى‚肽‚¢پB–³”_–ٍ‚¾‚ئ–ط‚àŒ’چN‚إ‚¢‚ç‚ê‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚»‚ê‚ةپA‚±‚جژR‚©‚çگ…–“‚جٹC‚ة”_–ٍ‚ً—¬‚µ‚½‚‚ب‚¢‚ٌ‚إ‚·پv‚ئپA“V–ى‚³‚ٌ‚ح‚«‚ء‚د‚èپB
ژèٹش‚ھ‚©‚©‚éچف—ˆژي‚ًˆç‚ؤ‚é
‚¨کb‚ًژf‚¢‚ب‚ھ‚çپA‰ü‚ك‚ؤچف—ˆژي‚ج’ƒ‰€‚ًŒ©‚é‚ئپA‚ئ‚±‚ë‚ا‚±‚ë—t‚ء‚د‚ھگش‚ف‚ھ‚©‚ء‚ؤ‚¢‚½‚èپA‚±‚ٌ‚à‚è‚ئ–خ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚èپB‘}‚µ–ط•c‚©‚çˆç‚ؤ‚é•iژي‚ج’ƒژ÷‚حپAچھ‚ج’£‚è‚ھگَ‚‚ؤ”ى—؟‚ھŒّ‚«‚â‚·‚¢”½–تپAٹ±‚خ‚آ‚ةژم‚©‚ء‚½‚èپA•aٹQ’ژ‚ة‚و‚é”يٹQ‚ھچL‚ھ‚è‚â‚·‚©‚ء‚½‚è‚·‚é‚ئ‚¢‚¤ƒfƒپƒٹƒbƒg‚àژ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
ˆê•ûپAƒ^ƒl‚©‚çˆç‚آپiژہگ¶پjچف—ˆژي‚ج’ƒژ÷‚حپA‘¾‚¢ژ©چھ‚ً’n’†گ[‚‚ـ‚إگL‚خ‚·‚½‚كگ¶–½—ح‚ھ‹‚پAژ÷—î‚ھ’·‚¢‚ج‚ھ“ء’¥‚إ‚·پB‚ـ‚½پA‘½—l‚بگ«ژ؟‚ج’ƒژ÷‚ھچ¬چف‚µ‚ؤ’ƒ‰€‚ًŒ`گ¬‚·‚邽‚كپA•aٹQ’ژ‚ج”يٹQ‚àŒہ’肳‚ê‚ـ‚·پB‚»‚ج•ھپA”_–ٍ‚â”ى—؟‚جڈ•‚¯‚ً•K—v‚ئ‚µ‚ب‚¢‚±‚ئ‚àƒپƒٹƒbƒg‚¾‚ئŒ¾‚¢‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپA‰ü—ا‚³‚ꂽ•iژي‚ئ‚حˆظ‚ب‚è1ٹ”‚²‚ئ‚جŒآگ«‚ھ‹‚پA—t‚جگL‚ر‚éƒXƒsپ[ƒh‚âگF‚ب‚ا‚ح‚ـ‚؟‚ـ‚؟‚إ‚·پB
‚»‚ج‚½‚كپA‹@ٹB‚إˆê‹C‚ةژûٹn‚·‚é‚ئ’ƒ—t‚ھ•s‘µ‚¢‚ة‚ب‚è‚ھ‚؟پB“¯‚¶ڈَ‘ش‚ج—t‚ًˆê‚آ‚¸‚آٹm”F‚µ‚ب‚ھ‚çژè“E‚ف‚·‚邱‚ئ‚إ•iژ؟‚ھˆہ’è‚·‚é‚ج‚إ‚·پBپu‚إ‚àپA’ƒ“E‚ف‚ج–¼گl‚ھ‚ا‚ٌ‚ب‚ةٹو’£‚ء‚ؤ‚àپA1“ْ‚ة1kg‚ظ‚ا‚µ‚©ژûٹn‚إ‚«‚ب‚¢‚ٌ‚إ‚·‚وپv‚ئ‚ج‚±‚ئپBژè“E‚ف‚ح‚ئ‚ة‚©‚گlژè‚ج‚¢‚éچى‹ئ‚ب‚ج‚إ‚·پB
‚±‚ê‚ç‚ج‚¨’ƒ‚جچح”|•û–@‚ب‚ا‚ً‚«‚؟‚ٌ‚ئ”گM‚·‚邱‚ئ‚إپAپuچف—ˆژي‚ج•iژ؟‚ج‡€ƒuƒŒ‡پ‚ًپAپwŒہ‚è‚ب‚ژ©‘R‚ة‹ك‚¢ٹآ‹«‚ج’†‚إˆç‚آ‚¨’ƒ‚¾‚©‚çپA‹ژ”N‚ئچ،”NپA‚±‚ج’ƒ‰€‚ئŒü‚±‚¤‚ج’ƒ‰€‚ج–،‚ھˆل‚¤‚±‚ئ‚à‚ ‚邾‚낤پx‚ئپAٹy‚µ‚ف‚ئ‚µ‚ؤ‘¨‚¦‚ؤ‚‚¾‚³‚é•û‚à‚¢‚é‚ٌ‚إ‚·‚وپv‚ئکb‚µ‚ـ‚·پB
‚»‚µ‚ؤڈخ‚¢‚ب‚ھ‚çپAپuژ‘م‚ة‹tچs‚·‚é‚و‚¤‚إ‚·‚¯‚اپAچ،Œم‚حچف—ˆ‚ج‚¨’ƒ‚ً‘‚â‚·‚آ‚à‚è‚إ‚¢‚é‚ٌ‚إ‚·پB‚»‚µ‚ؤپA’ڑ”J‚ةژè“E‚ف‚µ‚ؤچى‚邨’ƒ‚ة—ح‚ً“ü‚ê‚ؤ‚¢‚«‚½‚¢پB–{—ˆ‚ج‚¨’ƒ‚ج–،‚ً“`‚¦‚½‚¢پv‚ئکb‚µ‚ـ‚·پB
—خ’ƒ‚ج•iژي‚إچى‚éڈa‚ف‚ج‚ب‚¢‡€کaچg’ƒ‡پ
’ڑ”J‚ةژè“E‚ف‚µ‚½Œم‚حگ»’ƒچH’ِ‚ضپBپu“V‚جگ»’ƒ‰€پv‚إ‚حپA‹ك”NپA—خ’ƒ‚و‚èƒIپ[ƒ_پ[‚ھ‘‰ء‚µ‚ؤ‚¢‚éچg’ƒ‚ة—ح‚ً“ü‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚¨’ƒ‚حپAژûٹn‚µ‚½’ƒ—t‚ً‚ا‚ج‚و‚¤‚ةگ»’ƒ‚·‚é‚©‚ة‚و‚ء‚ؤپA—خ’ƒپi•s”چy’ƒپjپA‰G—´’ƒپi”¼”چy’ƒپjپAچg’ƒپi”چy’ƒپj‚ب‚ا‚ة•ھ‚©‚ê‚ـ‚·پB—خ’ƒ‚حپA“E‚ٌ‚¾گ¶—t‚ھ”چy‚µ‚ب‚¢‚و‚¤”M‚ً‰ء‚¦‚½Œم‚ة†‚ٌ‚إٹ£‘‡‚³‚¹‚½‚à‚جپB“V–ى‚³‚ٌ‚ح’†چ‘ژ®‚ئŒ¾‚ي‚ê‚éٹکàu‚è’ƒ‚جگ»–@‚ً—خ’ƒچى‚è‚ة—p‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‰G—´’ƒ‚حٹ±‚µ‚ؤڈ‚µ”چy‚µ‚½گ¶—t‚ً†‚فپA”M‚ً‰ء‚¦‚ؤ”چy‚ًژ~‚ك‚½Œم‚إٹ£‘‡‚³‚¹‚½‚à‚ج‚إ‚·پB
چg’ƒ‚حپAگ¶—t‚ً8ژٹش‚ظ‚ا‚¨‚¢‚ؤگ…•ھ‚ً”²‚¢‚ؤ‚©‚熔Pپi‚¶‚م‚¤‚ث‚ٌپj‹@‚ئ‚¢‚¤‹@ٹB‚إ†‚ف‚ـ‚·پB’ƒ—t‚حپA‹‚†‚ق‚ئگF‚حڈo‚ـ‚·‚ھڈa‚‚ب‚èپAŒy‚†‚ق‚ئڈa‚ف‚حڈo‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAگF‚àڈo‚ـ‚¹‚ٌپB‚»‚ج‰–”~‚ح“‚پA‚ـ‚½پA”چy‚ھƒ€ƒ‰‚ة‚ب‚ç‚ب‚¢‚و‚¤پA‹دˆê‚ة†‚ق‚±‚ئ‚à‘هگط‚إ‚·پB‘@ˆغ‚ب‚ا‚ھ‚ظ‚®‚ꂽ‚çپA‰·“x‚ئژ¼“x‚ً’²گ®‚µ‚ؤ”چy‚³‚¹‚ـ‚·پB‚·‚é‚ئ’ƒ—t‚حگش‚•د‰»‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚جŒم‚ة”M‚ً‰ء‚¦‚ؤ”چy‚ًژ~‚كپAٹ£‘‡‚³‚¹‚ؤٹ®گ¬‚إ‚·پB10kg‚جگ¶—t‚ھپAگ»•i‚ة‚ب‚é‚ئ2kg‚ظ‚ا‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB
چ،‚حچg’ƒگê—p‚ج•iژي‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپA—خ’ƒ‚ئ“¯‚¶•iژي‚ج’ƒ—t‚ً”چy‚³‚¹‚ؤچى‚ء‚½‚à‚ج‚حپAڈa‚ف‚ھ‚ب‚‚ـ‚ë‚â‚©‚ب–،‚ھ‚·‚é‚ج‚ھ“ء’¥پBگS’n‚و‚¢Œم–،‚ًٹy‚µ‚ك‚釀کaچg’ƒ‡پ‚ئ‚ب‚é‚ج‚إ‚·پB“V–ى‚³‚ٌ‚ھچى‚éچg’ƒ‚حپAگ»’ƒ’iٹK‚إ‚ج‰خ“ü‚ê‚جژd•û‚âپA“ئژ©‚ةچH•v‚ًڈd‚ث‚½”چy‹Zڈp‚ب‚ا‚ة‚و‚èپAˆê‘wŒآگ«‚ھ‹‚پAˆَڈغ“I‚ب–،‚ي‚¢‚ةژdڈم‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
‚»‚µ‚ؤپAپu–³”_–ٍ‚إچح”|‚·‚é‚ئپAچg’ƒ‚ج–،‚ةƒLƒŒ‚ھڈo‚ؤ‚‚é‚ٌ‚إ‚·‚وپv‚ئ“V–ى‚³‚ٌپB‚»‚ج•iژ؟‚ئ–،‚ي‚¢‚حچ‚‚•]‰؟‚³‚êپAپuڈ¬“¤‚ة•‰‚¯‚ب‚¢ژه’£‚ھ‚ ‚éپv‚ئپA—rم»‚إ’m‚ç‚ê‚éکV•ـکa‰ظژq“X‚جپu‚ئ‚ç‚âپv‚جچg’ƒ—rم»‚جŒ´—؟‚ةژg—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ظ‚ا‚إ‚·پB
‡€کaچg’ƒ‡پ‚ً‚¨‚¢‚µ‚‚¢‚½‚¾‚
’ڑ”J‚ةژٹش‚ً‚©‚¯‚ؤچى‚ç‚ꂽکaچg’ƒپBƒ|ƒCƒ“ƒg‚ً‰ں‚³‚¦‚ؤ‚¨‚¢‚µ‚‚¢‚½‚¾‚«‚½‚¢‚à‚ج‚إ‚·پB2پ`3گl•ھ‚إ‚ ‚ê‚خپA’ƒ—t5g‚ة‘خ‚µ‚ؤپA•¦“«’¼Œم‚ج98“x‚‚ç‚¢‚ج”M‚¢‚¨“’‚ً400cc‚ظ‚ا—pˆسپB—eٹي‚ح’ƒ—t‚ھ“®‚«‚â‚·‚¢‚و‚¤پAٹغ‚¢Œ`‚ً‚µ‚½‘ه‚«‚ك‚ج‚à‚ج‚ھ‚¨‚·‚·‚ك‚إ‚·پB
’ƒ—t‚ھ‘S‘ج‚ةچs‚«“n‚é‚و‚¤‚ة“’‚ً’چ‚¬پA—t‚ً‘خ—¬‚³‚¹‚ـ‚·پB’ƒ—t‚ھگ…•ھ‚ًڈ\•ھ‹z‚ء‚ؤ–c‚ç‚ق‚ـ‚إ3پ`5•ھ‚ظ‚ا‘ز‚؟پA•ت‚ج—eٹي‚ةچ—‚µ“ü‚ê‚ـ‚·پB‚±‚±‚إ’ƒ—t‚ً‚µ‚ء‚©‚èگط‚邱‚ئ‚إ–،‚ھ‹دˆê‚ة‚ب‚èپA–،‚ج•د‰»‚à–h‚¬‚ـ‚·پBکaچg’ƒ‚حپA“’‚ً’چ‚¢‚¾ŒمپA’ٹڈoژٹش‚ً’·‚‚µ‚ؤ‚àڈa‚ف‚ھڈo‚ة‚‚¢‚ج‚ھٹً‚µ‚¢“_پB
“§–¾ٹ´‚ج‚ ‚éàوàكگF‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ؤ”ü‚µ‚پAŒû‚ة‚·‚é‚ئƒXƒb‚ئ‘ج’†‚ةچs‚«“n‚ء‚ؤ‚¢‚‚و‚¤پB“ء‚ةچف—ˆژي‚جچg’ƒ‚ح–ىگ«–،‚ة‚ ‚س‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپAچپ‚è–L‚©پBŒû‚ة‚·‚éگl‚ً–£—¹‚·‚é–،‚ھ‚µ‚ـ‚·پB•iژي‚ة‚و‚ء‚ؤ‚حپA‰ؤ‚حگ…‚¾‚µ‚ة‚µ‚ؤ‚à‚¨‚¢‚µ‚¢‚ئ‹³‚¦‚ؤ‚‚ê‚ـ‚·پB
‚¨’ƒچى‚è‚ج–£—ح‚ة‚آ‚¢‚ؤپAپu“ڑ‚¦‚ھ‚ب‚¢‚ئ‚±‚ëپAگ³‰ً‚ھ‚ب‚¢‚ئ‚±‚ë‚إ‚·‚ثپv‚ئ“V–ى‚³‚ٌ‚حŒ¾‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ج’n‚ةگ¶‚ـ‚êˆç‚آ‚¤‚؟پA“–‚½‚è‘O‚ج‚و‚¤‚ة•ƒگe‚ئˆêڈڈ‚ة’ƒ‰€‚إژdژ–‚ً‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½“V–ى‚³‚ٌپB—c‚¢چ ‚©‚炸‚ء‚ئŒ©‚ؤ‚«‚½چف—ˆژي‚جŒأ–ط‚ًŒ©‚ب‚ھ‚çپu‚¨’ƒ‚ج–ط‚ة‚ح‚ج‚ر‚ج‚ر‚ئˆç‚ء‚ؤ‚à‚ç‚¢‚½‚¢پB‚»‚±‚©‚ç‰ءچH‚ج’iٹK‚إ‚¢‚©‚ة‚¨‚¢‚µ‚‚µ‚ؤ‚¢‚‚©‚حژ„‚½‚؟‚جژdژ–‚إ‚·پv‚ئکb‚µ‚ـ‚·پB
‚¨’ƒ‚ح•é‚炵‚ة‹ك‚¢‚ئ‚±‚ë‚ة‚ ‚é‚à‚جپA‹CŒy‚ةٹy‚µ‚ٌ‚إ‚à‚炦‚邱‚ئ‚ھˆê”ش‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚é“V–ى‚³‚ٌپB‚»‚ج‚½‚كپAژèٹش‚ج‚©‚©‚é–³”_–ٍچح”|‚ً‘±‚¯‚ؤ‚àپA“ْپX‚ج•é‚炵‚ةژو‚è“ü‚ê‚ؤ‚à‚炦‚é‰؟ٹi‘ر‚إ”ج”„‚µ‚½‚¢‚ئŒ¾‚¢‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤپAژ©•ھ‚½‚؟‚ھˆç‚ؤ‚½’ƒ—t‚ًژ©•ھ‚½‚؟‚إ‚¨‚¢‚µ‚گ»’ƒ‚·‚邱‚ئ‚إپA‚¨’ƒ–{—ˆ‚ج–،‚ي‚¢‚ًپA‚à‚ء‚ئ‚½‚‚³‚ٌ‚ج•û‚ةپA‚à‚ء‚ئگg‹ك‚ةٹ´‚¶‚ؤ‚à‚炦‚ê‚خ‚ئ—ح‹‚Œê‚è‚ـ‚·پB
’ƒ‰€‚حŒ©ٹw‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«پA—خ’ƒ‚âکaچg’ƒ‚جژژˆùپAچw“ü‚à‰آ”\‚إ‚·پB‚ـ‚½پAپu‚¢‚ë‚¢‚ë‚ب•û‚ة—ˆ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¢‚ؤپA‚¨’ƒ‚جکb‚à‚µ‚½‚¢‚ٌ‚إ‚·‚و‚ثپv‚ئ“V–ى‚³‚ٌپi’ƒ‰€‚إچى‹ئ’†‚ج‚±‚ئ‚ھ‘½‚¢‚½‚كپA—ˆ‰€‚جچغ‚حژ–‘O‚ةکA—چ‚ًپjپBپu—ح‚ج‚ ‚邨’ƒ‚ًˆù‚ق‚ئپAŒ³‹C‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚وپv‚ئŒ¾‚¤گ؛‚ح’£‚è‚ھ‚ ‚ء‚ؤڈ_‚ç‚©‚پAژRٹش‚ة‹؟‚¢‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚µ‚½پB
“V‚جچg’ƒ‚ھ‚إ‚«‚é‚ـ‚إ
‹@ٹB‚ًژg‚¤‚±‚ئ‚ب‚پA‘S‚ؤگl‚جژè‚إچى‚éچg’ƒ‚جگ»‘¢چH’ِ‚ً“V–ى‚³‚ٌ‚ة‹³‚¦‚ؤ‚¢‚½‚¾‚«‚ـ‚µ‚½پB
3
—t‚ء‚د‚ھ‚؟‚¬‚ê‚ب‚¢‚و‚¤پAگ…•ھ‚ً‹دˆê‚ة‚·‚éƒCƒپپ[ƒW‚إپA15•ھ‚ظ‚ا—D‚µ‚†‚ف‘±‚¯‚ـ‚·پB1‰ٌ‚ة†‚ك‚é—ت‚ح80پ`100ƒOƒ‰ƒ€‚ظ‚اپB†‚فƒ€ƒ‰‚ھ‚ب‚¢‚و‚¤‹C‚ً”z‚è‚ـ‚·پB
Information

“V‚جگ»’ƒ‰€
گ…–“ژs‚جژRٹش‚ةچL‚ھ‚釀“V‹َ‚ج’ƒ”¨‡پ‚إچح”|‚·‚éکaچg’ƒ‚ھگl‹CپBژ÷—î90”N‚جچف—ˆژي‚ً‚ح‚¶‚كپA11ƒwƒNƒ^پ[ƒ‹‚ج’ƒ‰€‚إ‚حپAپuˆہ‘S‚إ‚¨‚¢‚µ‚¢‚¨’ƒ‚ًچى‚肽‚¢پv‚ئ‚جژv‚¢‚©‚çپA–³”_–ٍپA–³”ى—؟چح”|‚ھ‘±‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پy“V‚جگ»’ƒ‰€پz
پuگX‚ئژي‚ئ‚¨’ƒپvپ~پu“V‚جگ»’ƒ‰€پvچg’ƒƒZƒbƒg
چإچ‚•iژ؟‚ج–{ٹiچg’ƒ‚ً‹l‚ك‚½ٹت“ü‚è’ƒ—t‚ئپAگl‹C‚جچg’ƒƒeƒBپ[ƒoƒbƒO3“_پu“V‚جڈمچg’ƒپvپAپu“V‚ج‚µ‚ه‚¤‚ھچg’ƒپvپAپu“V‚ج‹à–طچزچg’ƒپv‚ً‹l‚ك‚ ‚ي‚¹‚½ƒMƒtƒgƒZƒbƒgپB
پ،3,240‰~پiگإچپjپy15ƒZƒbƒgŒہ’èپz
پE–{ٹiچg’ƒƒٹپ[ƒt30gٹت“ü‚èپA“V‚جڈمچg’ƒ2gپ~10پA“V‚ج‚µ‚ه‚¤‚ھچg’ƒ2.5gپ~10پA“V‚ج‹à–طچزچg’ƒ2gپ~10


















